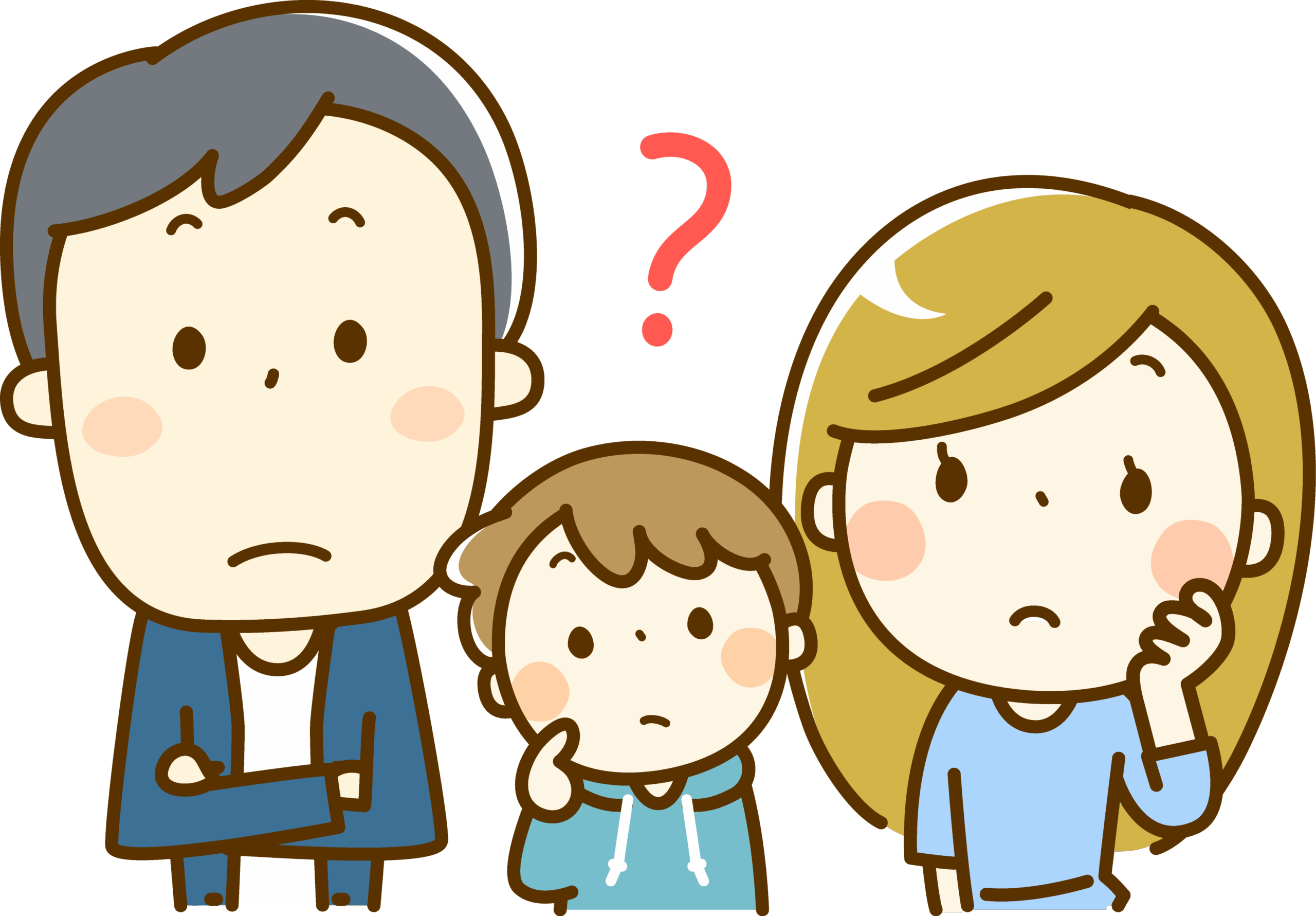町には様々な病院や診療所があります。その一方で、鍼灸院や整骨院などの施術所も多くあります。今の社会では、現代医学と東洋医学の両方が、身近な医療として多くの人に利用されています。
では、現代医学と東洋医学は、それぞれどのようなことができる医学なのでしょうか。今回は、現代医学と東洋医学のできることについて、またこれらの医学をどのように活用していけばよいかについて、私なりの考えをまとめてみます。少し長くなりますが、お時間のある時に読んでいただけたらと思います。(この文章は私の個人的な意見であることをご承知おきください)
(似たようなテーマで切り口の異なる記事を過去に書いています。よろしければこちらもご覧ください。現代医学と東洋医学の違いと特徴)
現代医学のできること
現代医学は一体どんなことができる医学なのでしょうか。考え方は様々あると思いますが、私は大きく分けて、次の二つだと思っています。
- 器質的な異常を調整する
- 機能的な異常を調整する
これらについて、順に見ていきたいと思います。
現代医学は器質的な異常の処置に優れている
まず、器質的な異常とはなんでしょうか。それは一言で言うと、体の形の異常です。
体の不調には様々ありますが、その中でも、骨折、肉離れ、腫瘍、腫瘤など、体の形が元の状態から変化して、おかしな形になってしまったものを、器質的な異常といいます。
そして現代医学は、整復、固定、手術など、器質的な異常への対処法を多く備えています。現代医学は、器質的な異常の調整に優れているのです。
骨の整復、固定や、靭帯の移植、腫瘍の除去などで、体をできる限り元の状態に近づけて、生活に支障がないところまで調整することが可能です。
変化してしまった体の形を、体の持つ修復力を遥かに超えて、元の状態に近づけることができる、この点が現代医学の優れた点の一つだと思います。
機能的な異常には対処療法としての処置ができる
次に、機能的な異常とはなんでしょうか。同様に一言でいうと、体の働きがおかしくなることで引き起こされた異常です。
機能的な異常とは、血圧が高い、血糖値が高い、胃酸やホルモンの分泌が多いなど、体の働きが正しくないために引き起こされる異常のことをいいます。機能的な異常の範囲は広く、血圧や血糖値など、数値として捉えられるものから、胃の動きが悪い、便秘が続く、体が重い、など数値として捉えられないものも含まれます。
また時に、器質的な異常と機能的な異常が同時に現れる場合があります。そのような場合の多くは、器質的な異常によって体の形が変化し、それによって機能的な異常が引き起こされています。例えば、内分泌器官に腫瘍ができ、それによってホルモンが異常に分泌されてしまう、といった状態です。そのためこのような異常は、器質的な異常に分類されます。
つまり機能的な異常とは、器質的には何も問題がないのに(体の形に大きな変化ががないのに)、体の働きがおかしくなることで引き起こされた異常、ということになります。
そして、現代医学は機能的な異常に対しても処置を行うことができます。
血圧を下げる、脂質代謝を調整する、足りないホルモンを補充する、消化酵素を補充する、胃の粘膜を保護する、といった薬を使って、体の働きの失調によって引き起こされた異常を、正しい状態へと調整していきます。
ただ、これらはあくまでも対処療法であり、異常そのものが起きないようにするものではありません。ですので、異常が引き起こされる、という体の状態が改善されない限りは、処置を続ける=薬を飲み続ける、必要に迫られます。
とは言っても、一つの異常が他の問題を引き起こすことはよくあるので、それを抑えることができる、と言う点からも、現代医学の処置が有用である場合は多いと思います。
現代医学のできること
このように現代医学は、器質的な異常と機能的な異常の両方に対処することができます。特に器質的な異常に対しては優れた調整力を有しています。また機能的な異常に対しては対処療法を行うことができますが、異常を引き起こす原因に対してのアプローチは苦手です。
東洋医学のできること
次に、東洋医学のできることを見ていきます。それは東洋医学の持つ、「体の働きを正しくする」という作用に関わります。この作用を、先の現代医学のできることに当てはめて考えると、東洋医学のできることは、次の二つになると思います。
- 器質的な異常を調整する(体の調整能力の範囲内で)
- 機能的な異常を調整する
これらについて見ていきます。
東洋医学は体の調整能力の範囲内で器質的な異常を調整できる
現代医学と同じく東洋医学も、器質的な異常に対処することができます。ただしそれは、あくまでも体の持つ調整能力でカバーできる(調整能力の範囲内の)異常に対してです。東洋医学は現代医学のように、体の調整能力を超えた異常を調整することは難しいのです。
では、体の調整能力の範囲内、とはどういうことでしょうか、例として骨折を考えてみます。
骨折にも種類があり、ここでは骨が完全には折れておらず、部分的に繋がった状態の骨折(不全骨折)を挙げてみます。
この場合は東洋医学でも対処が可能で、体の外から骨の位置を調整して、添木などで固定し、体の修復力を高める処置を行うと(全ての内臓の働きを高める+患部への血流を良くする、など)、骨折を早く回復させることができます。
(確かに東洋医学でも対処が可能ですが、実際は、骨の状態の確認(X線)と、骨の位置の調整と固定までは、現代医学で処置した方が安全です。)
どうしてこの場合は、東洋医学で対処できるのでしょうか。それは、治癒のために求められるものが「骨折面の接合」であり、体が通常行っているタスクを超えない=体の修復能力の範囲内、だからです。東洋医学で体の働きを正しくして、修復力を高めることが、回復への良い効果をもたらすのです。
次に、骨が体の中で砕けてしまった場合(粉砕骨折)を考えてみます。この場合は、東洋医学で対処ができるでしょうか。
それは難しいと思われます。まず、骨が体の中でバラバラになっているので、体の外から骨の位置を調整することが出来ません。また、体に任せることで、バラバラになった骨が自然に適切な位置に移動していく、ということも起こり得ません。回復のためには、現代医学の手を借りることになります。皮膚を切開して、バラバラになった骨の位置を直接調整し、状態によっては、プレートやボルトで骨と骨を固定したり、骨移植が必要となることもあります。
この場合は、治癒のために求められるものが、体が通常行っているタスクを超えている=体の修復能力の範囲を超えている、のです。ですので、東洋医学では対処することが難しくなります。
ただ、骨の位置の調整や、ボルトでの骨の固定など、現代医学の処置が一通り終わった後は、東洋医学の処置が効果を発揮します。何故ならば、現代医学の処置が完了した後は、治癒のために求められるものが「骨折面の接合」となり、体の修復能力の範囲内となるからです。東洋医学の処置で体の修復作用を高めると、回復のために良い効果があります。
このように、東洋医学は器質的な異常に対して、体の持つ調整能力の範囲内であれば、対応することができます。それを超える場合は、現代医学の手を借りるべきです。ただ後者の場合でも、現代医学の処置と合わせて東洋医学の処置を行うことで、回復を早めることができます。
東洋医学はより原因に近い部分の調整ができる
次に、機能的な異常について見ていきます。
東洋医学は機能的な異常に対しても対処することができます。そして、現代医学より原因に近い部分の調整を行うことができます。
どういうことかと言うと、現代医学では、機能的な異常に対して対処療法としての処置を行いますが、東洋医学では異常そのものではなく、異常を生み出している体の部分にアプローチして、その働きを正しくすることで、異常を抑えていくことができるのです。
先の血圧を例に挙げると、心臓の働きが亢進して血圧が上がっているのであれば、心臓の働きを正しくすることで血圧を調整し、また腎臓の働きが悪くて血圧が上がっているのであれば、腎臓の働きを整えることで血圧を調整していきます。
実際の処置においては、これは東洋医学の特徴でもありますが、異常の起こっている部分だけに注目することはせず、体全体の働きを正しくすることを試みます。なぜならば、問題とする異常が体のどこから引き起こされているかを特定することが、多くの場合難しいからです。血圧であれば心臓が原因と考えがちですが、他の臓器や、自律神経に依存する場合もあります。また原因が一つでない場合もありますし、原因の原因….と言った具合に、思いもよらないところに、原因が隠されている場合もあります。ですので、東洋医学では体全体の調整を行うのです。
このように東洋医学では、機能的な異常に対して、現代医学よりも原因に近い部分の調整を行うことができます。
東洋医学が持つ現代医学とよく似た問題点
ただ、東洋医学にも現代医学と同様の問題があります。それは、調整の効果が一時的であることが多い点です。現代医学で薬を飲み続けなくてはいけなかったのと同様に、東洋医学では処置を頻繁に行わなくてはなりません。
ただし東洋医学の施術(鍼灸や整体などのボディケア)は、現代医学の薬(現代薬と表記します)にはない、次のような特徴があります。
(東洋医学の処置には漢方薬(湯液)もあります。ですが、私自身が漢方薬の臨床についての知識が少ないので、ここでは鍼灸や整体などのボディケアに関する話を中心に書いていきます。漢方薬については、この先に、私の個人的な考えをまとめています。)
それは、東洋医学の施術を繰り返すことで、体が元々持っている働きが回復して、正しい状態を維持できる期間が長くなることです。この身体機能の回復は東洋医学の施術ではよく見られます。
また東洋医学の施術は、現代薬のように、体に負担をかけません。現代薬は長く飲み続けると、薬の薬効成分を代謝、排泄する臓器に影響が及ぶことが懸念されています。これに対して東洋医学の施術は体の外からの調整なので、臓器に負担がかかることはほとんどありません。
このような点から、長期間処置を続ける場合には、東洋医学の方が体への負担は小さいと思われます。
東洋医学の調整力は現代医学ほど高くない
もう一つ、東洋医学には注意しなければならない点があります。それは、東洋医学の調整力は現代医学ほど高くない、ということです。
先に、東洋医学のできることは、体の働きの正常化と書きました。つまり、東洋医学の調整力は、体の持つ調整能力を引き出しているのに過ぎないのです。
これに対して現代医学は、体の持つ調整能力を超えた調整力を発揮します。
私たちの体には様々なことが起こります。時には体の調整能力を超えた処置を行わなければ、生命に危機が及んだり、長期的に健康を害する場合もあります。
例えば、感染症による高熱がそうです。体が発熱を促す目的は、病原菌の活動性を下げ、白血球の活動性を上げる点にありますが、この体の調整力に任せて、病原菌が除去されるのを待っていては、発熱によるダメージに体が耐えられない場合があります。こういった時は抗生物質や抗ウイルス薬で病原菌の勢いを弱めることが必要となります。
そこまで差し迫っていなくても、体の調整能力に任せていては問題がおこる場合もあります。例えば、膵臓の機能が落ちてしまってインスリンが十分に分泌されなくなってしまった場合などです。この場合も体に任せていては、血糖値が高い状態が続き、動脈硬化や全身の血管にダメージが入る危険性があります。こういった時も、現代医学の調整力に頼るべきだと思います。
また、先に挙げた粉砕骨折の場合もそうです。体の調整能力の範囲を超えているため、体に任せていては、正しい状態で骨が繋がらず、おかしな形に落ち着いてしまう(偽関節化)ことがあります。そうなると本来関節でないところが関節のように動くため、安定性がなくなってしまいます。このような場合も、現代医学の手を借りて、正しい位置で骨が接合できるように調整することが必要となります。
東洋医学のできること
色々と見てきましたが、東洋医学のできることは、現代医学と同じく器質的な異常の調整と、機能的な異常の調整です。ただし器質的な異常については、体の調整能力の範囲を超えないものが対象となります。そして、機能的な異常については、現代医学よりも原因に近いところの調整を行うことができます。
また、東洋医学の処置は、現代医学と同じく、頻繁に行う必要があります。ですが、処置によって身体機能の回復が促され、処置の頻度を落としていくことができる場合がよくあります。
そして、東洋医学の調整力は体の調整力を引き出しているのに過ぎません。体の調整力を超えた処置が必要な場合は、現代医学の手を借りた方が良いと思われます。
現代医学と東洋医学をどのように選んでいけば良いか
現代医学と東洋医学のできることを、それぞれ見てきました。では、私たちの日常生活において、これらの医学をどのように利用していくのが良いのでしょうか。私は次のように思っています。
- 健康であっても、病気を抱えていても(どのような器質的な異常、機能的な異常があっても)、東洋医学の施術(鍼灸、整体など)を定期的に受けて、体の働きを調整していく
- 健康維持に影響がある病気、怪我、体調不良(器質的な異常、機能的な異常)の場合は現代医学の処置を受ける
日常的には東洋医学、健康維持に影響があるときは現代医学
東洋医学の施術は体の働きを正常化することができます。ですので、健康であっても、病気を抱えていても、どんな状況でも(どのような器質的な異常、機能的な異常があっても)東洋医学の施術を受けることにはメリットがあります。
ですので、日常生活では、定期的に東洋医学の施術を受けて、体の働きを正常化していきましょう。
そして、健康維持に影響が及ぶ場合は、現代医学の処置を受けましょう。そもそも東洋医学の処置は、体の調整力を発揮しているにすぎません。ですので、これを超えた調整力が必要となる場合には、現代医学の処置が必要となります。
一つの目安としては、東洋医学の施術を定期的に受けても、体調が改善しない場合や、現代医学の検査ですぐに処置が必要と判断された場合などです。こういった時は、現代医学の処置を受けるようにしましょう。そしてその場合でも、現代医学に加えて東洋医学の施術を受けるのが良いと思います。
漢方薬について
ここまで読んでこられて「漢方薬はどうなの」と思われた方もおられると思います。ご承知の通り、東洋医学の処置には漢方薬(湯液)もあります。ここからはあくまでも私の個人的な意見ですが、私は漢方薬は、東洋医学の他の施術(鍼灸や整体など)とは性質が違うものだと思っています。
何故ならば、鍼灸や整体などのボディケアは、体の外から体の働きを調整していきますが、漢方薬は薬効成分を口から体に取り入れることで、体の働きを調整していくものだからです。薬効成分を口から取り込む以上、漢方薬は現代薬と同様に、体内での薬効成分の代謝を必要とし、その際に体に負担をかけます。つまり漢方薬は、東洋医学の処置の中では現代医学に近く、体への負担に気を配らなくてはならないものだと思われるのです。(ただ漢方薬は現代薬よりも純度が低いので、体への負担は現代薬より小さいと思います。)
(純度と体への影響については、こちらの記事もご覧ください。雑多なままがいいのでは)
どの程度影響があるかは、体の薬効成分を代謝する能力によりますので、個人差もありますし、加齢によっても変化が出てくると思います。ですので漢方薬を長期間使用する場合は、「薬の効きめ」というメリットと、「体に負担がかかる」というデメリットを意識して、どちらが大きいかを観察しながら、使用していく必要があると思います。
また、現代薬を飲んでいる場合には、飲み合わせにも注意が必要です。このあたりは医師に確認する必要があると思います。
現代医学と東洋医学ができることを理解して、健康に活用していこう
現代医学と東洋医学のできることと、それらを踏まえた活用に仕方について見てきました。現在の社会では、一般的に医学と言えば現代医学ですので、「体のことは病院で」と思われている方がほとんどだと思います。ですが、現在の生活環境は体に負担をかけるものが徐々に増えており、現代医学だけで健康の維持するのは難しくなってきていると思います。
町には東洋医学の施術所が多くあります。そういった施術所を定期的に利用して、健康維持に意識を配ることが、これからは必要になっていくと思います。ぜひご自分にあった施術所を見つけて、健康維持に活用して下さい。