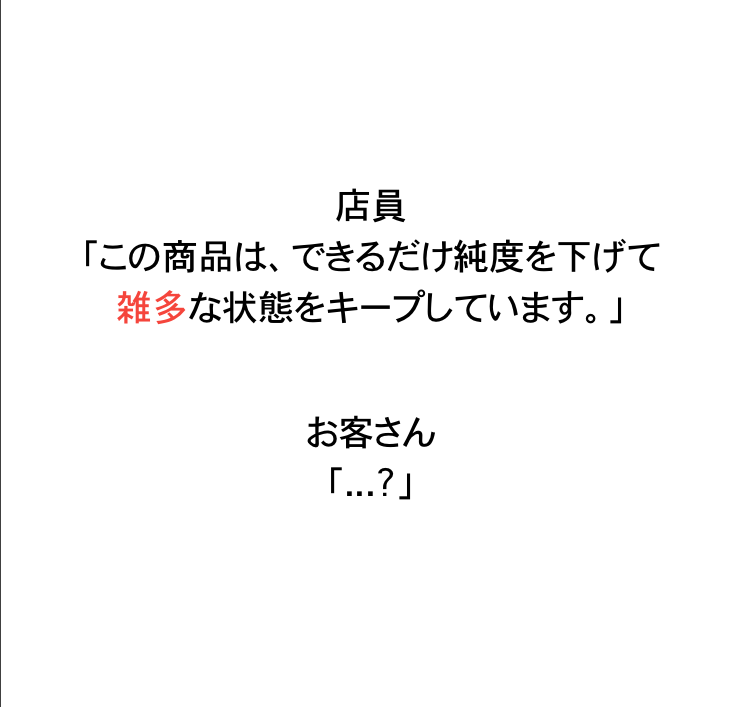健康のためには、体に良いものを、なるべく多く取り入れたいものです。となると普通は、必要なものをできるだけ純度の高い状態で、と思ってしまいます。ですが、私はあまり純度を上げずに、なるべく雑多なまま取り入れる方が、良いのではないかと思っています。
なぜそう思うのかというと、それは、その方が私たちの体に合いそうだからです。
今回は「雑多な方が良い」ということについて、まだ分からないことや、推測でしかない点も多いのですが、今の段階での考えをまとめてみようと思います。お付き合いいただけると嬉しいです。
純度が高いものより雑多なものの方が優しい
化学肥料をあげすぎると根が痛む
我が家は、少しですが庭で野菜を育てています。化学肥料を使わずに、有機肥料やぼかし肥料を使っています。なぜかというと、化学肥料を使うと、根を痛めることがあるからです。
化学肥料は植物が育つのに必要な栄養素(主にリン、カリウム、窒素など)を科学的に抽出して粒にしたものです。植物が、必要な栄養素をすぐに吸収できるので、早く効果が現れるという優れた点があります。反面、与えすぎると根が痛んだり、病気になったりするそうです。
有機肥料は、米糠、油粕、鶏糞など、植物が必要な栄養素を含んだ有機物です。土に混ぜると微生物がこれを分解し、土に窒素やリンなどの栄養素を補給することができます。また、ぼかし肥料は、有機肥料を発酵させた(微生物にある程度分解させた)ものです。
有機肥料やぼかし肥料は、すぐに効果が出ることはありませんが、時間と共に効果が出て長く効きます。そして化学肥料のように根を痛めたり、病気になることはあまりありません。
このことから、植物に肥料を与える際、純度の高い化学肥料よりも、雑多な有機肥料やぼかし肥料を使う方が、植物にとっては優しいように思われるのです。
現代医学の薬は体への負担が大きい
薬についても、同じことが言えます。
現代医学の薬は、体に作用を及ぼす物質のみを、科学的に抽出して、錠剤などにまとめたものです。効果が高く、即効性もあるのですが、反面、副作用の問題があります。また目に見えた副作用がなくても、長く薬を飲み続けている人の体を見ると、必ず肝臓に負担がかかっています。
一方、漢方薬はどうでしょうか。
漢方薬は、体に効能のある食物や鉱物を、煮たり、焼いたりして濃縮したものです。有効成分を科学的に抽出する、現代医学の薬よりは雑多な状態です。漢方薬は現代医学の薬ほどシャープには効きませんが、効き目が穏やかで、長く服用することができます。
薬を見ても、私たちの体に優しいのは、雑多な漢方薬の方ではないかと思われます。
食品も雑多な方が優しそう
食品はどうでしょうか。私の経験では、食品も雑多な方が負担が少ないように思われます。
あまり症例は多くはないのですが、プロテインやサプリメントを多く飲んでいる方を見ていたことがあります。その時に気になっていたのは、消化器にひどく負担がかかっていたことです。
こういった純度の高い食品は、消化吸収にパワーが必要なのでしょう。
このように食品も、加工された純度の高い状態ではなく、そのままの雑多な状態でいただくのが、体には優しいようです。
自然界も私たちの体も、そもそもは雑多
先ほど庭の話が出てきましたが、庭は管理が大変です。何が大変かというと、雑草です。
庭の雑草を見ていると、一種類ではないことに気がつきます。いろんな種類の雑草がひしめき合っていて、ある種類が増えてくると他の種類が減ってきて、またある種類が増えると他が減る、ということを繰り返しています。おそらく庭の何かの条件と、気温や湿度、日照時間などにより、どの種類が増えるのか、が決まるのでしょう。なんとなく秩序があり、バランスがとられているのです。
このように自然界は、そもそも雑多なのです。
では、私たちの体はどうでしょうか。
実は、体の中には多くの菌類が住み着いています。そしてそれらの菌類は、私たちが食べたものや、感情・思考など心の状態に影響を受けて、ある種類が増えたり、ある種類が減ったり、を繰り返しています。庭の雑草と同じように、何かの秩序に従い、バランスをとりながら繁栄したり衰退したりしているのです。
つまり、私たちの体にも自然界のバランスが存在し、雑多な状態で安定していると思われるのです。
雑多なものは豊かさにつながる
私たちには雑多が合う
このように見てくると、私たちの体には、純度の高いものより、雑多なもののほうが、合うように思えてきます。
純度の高いものは、もともと雑多な自然界のバランスを崩すのでしょう。
杉や檜などの人工林がその例です。単一種の杉や檜を植林した人工林は、自然に発生し維持している天然林よりも、生物の多様性が劣ります。人工林では、ある決まった種類の草や樹木しか育たないため、そこに生きる動植物が限られ、生態系が単純になってしまうのです。
私たちの体にも、自然界のバランスがあります。それを崩さないためにも、純度の高いものを取り入れるのは、控えた方が良さそうです。過度に加工されて純度が高くなったものを避け、雑多なままのものを頂くのが、体にはきっと合うのです。
雑多なものが豊かさを育む
また同じことが、知識や経験についても言えると思います。
タイムパフォーマンスが求められる世の中になってきたからか、結果や結論のみが求められる風潮があるようです。ですが、結局どうなったか、という物事のコアの部分をなぞるだけでは、知識や経験の多様性は育ちにくいように思います。
お皿にステーキだけが載っていて、付け合わせが何もないような状態です。
コアに至るまでの過程を追体験し、全体に点在する、一見必要なさそうなものも取り入れて咀嚼することで、知識や経験の豊かさが育まれるのではないでしょうか。
きっとこういった雑多な知識や経験が、人の豊かさを作るのだと思います。